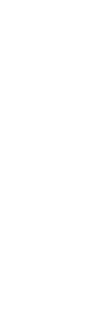- 第2回日本の藍染 その1
- 2018/12/01
-
日本古来の藍草は山藍(トウダイグサ科)とされ、
山陰に自生しているものを採取し、布に擦り付けて染めていたと言われています。
ただし古い文献における『青』が指す色はブルーからグリーンまで幅広いため、その色味は定かではありません。
更に言えば、山藍は藍染に必要な色素インディゴを含有していないとの研究もあります。
残念ながらこの山藍で染めたとされる品は現存しておらず、今となっては文献にのみ残された幻のような存在です。
そして古墳時代になると、その後の日本の藍染を支えることとなる蓼藍(タデアイ)が、大陸から日本にもたらされました。
初めのうちはやはり生葉を布に擦り付けたり、絞った汁で染める簡易的な染めをしていたようです。
ただこの方法には難点があり、藍の葉が茂る夏場しか染められませんし、麻のような植物繊維は染まりまりません。
また繰り返し染めても濃い色に染めることは困難なのです。
しかし奈良~平安時代の品には、生葉で染めたとは考え難いほど濃く染まった藍の色がみられ、染色技法の発達が認められます。
その代表が東大寺正倉院に伝わる藍の絹縄『縹縷』(はなだのる)で、現存する日本の藍染の品としては最古の品とされています。
これは奈良時代752年の大仏開眼会(大仏完成のお披露目儀式)の際、大仏様の眼に墨を点じる筆にこの絹縄を結び、参列者は皆でこれを握って功徳に預かったとされる何ともありがたい品です。
どのように染めたのかはわかりませんが、色味の濃さを見る限り、沈殿法が見出されていたのかもしれません。
1200年前に染められた藍が未だに色褪せずに残っていることは驚きですし、藍染本来の堅牢度の高さを知ることができます。
ところでこの頃、藍染の衣はほんの一握りの高貴な身分の人々にのみ、身につけることが許された色でした。
染色技法の問題により、貴族が着る絹の衣は染められても、庶民が着る麻(植物繊維のもの)などはまだ染められなかったことも一因かもしれません。
日本中が藍染で溢れるのはまだまだ先の話です。
やがて時代とともに藍染の技法は発達し、藍の葉を発酵、保存して使う建染めの技法が確立します。
ようやく季節を問わず染めることも、麻や綿を染めることも、またより濃い色に染めることも可能になったのです。
そうして日本の藍染文化はどんどん盛り上がっていきます。
次回、そんな藍染文化の最盛期である室町~江戸、そして衰退の一途を辿る現代までの遍歴をお話しします。