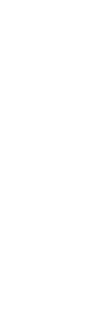- 第8回ヨーロッパの藍染
- 2019/6/01
-
ヨーロッパの藍染と聞いてもあまりピンとこない方が多いかもしれませんが、はるか昔より藍染が行われてきました。
近頃はパステル染めと呼ばれて僅かに続けられているようです。
寒冷なヨーロッパでは、大青(たいせい)またはウォードと呼ばれる藍草が用いられます。
葉を捏ねて乾燥させたコカーニュと呼ばれる原料を、発酵させて染料にするそうです。
しかしこの大青にはいくつか問題点がありました。
まず葉っぱの色素の含有量がとても少なく、なんとインド藍の20分の1とまで言われています。
さらに大青は冴えた青色に染めることが難しく、またその染液の悪臭から人々に忌避されていました。
(発酵させるためにしばしば人の尿が使われたことも要因ではと思います。)
そのためヨーロッパにおいて藍染は好まれず、さらには青色が忌み嫌われる原因にもなります。
尚且つ青は、ローマ帝国にとって敵対する民族の瞳の色であり、
なおかつ戦の際に藍の染料で肌を青く塗って挑んできたこともあって、
野蛮で死を連想させる、汚く貧しいことの象徴として定着していたようです。
ですが中世になると転機が訪れます。
当時の喪服は前述の理由から青色でしたので、宗教画において聖母マリアを象徴する色として用いられるようになりました。
すると青色は徐々に好まれるようになり、王族の衣服に使われるまでになるのです。
今でも青はヨーロッパでとても人気のある色です。
大青の話に戻ります。
そうして一時は大きな富を産むほど盛んに大青の栽培と染めが行われましたが、
16世紀になるとやはり、ここにもインド藍が台頭します。
瞬く間にその地位を奪われてしまいました。
その後の繊維産業の染色はインド藍に切り替わり、
植民地であるインドやアメリカ、ブラジルなどで盛んにインド藍の工場が経営されました。
今となっては大青を使った藍染はすっかり影を潜めていますが、
南仏トゥールーズなど、かつて大青の栽培で大きな富を築いた街は当時の面影を残しているようです。